「もしかして、、他の子より育てにくい?」
そう思い始めたのは、長男が3歳の頃でした。
こだわりがとにかく強くて、くつしたの縫い目が気に入らない。どうしても受け入れられない。くつした履きたくない~(´;ω;`) 💢と毎日30分はこのやり取り。
しばらくすると保育園の先生からも「あのね、少し気になるところが…」と声をかけられるように。
初めは「男の子はそんなもの」「そのうち落ち着くよ」と周囲に言われてはいたものの、心配性な私の不安は日に日に大きくなっていきました。
この記事では、長男が発達障害(自閉スペクトラム症+ADHD)と診断されるまでに私が感じたサインや、発達相談〜診断確定までの流れを実体験ベースでお話しします。
同じように「なんとなく違和感があるけど、どうすればいいかわからない」と悩んでいるママのヒントになれば嬉しいです。
3歳頃から感じた“ちょっと違うかも”という違和感
長男が3歳になった頃、ふとした瞬間に「あれ??」と感じるようになりました。
もともと1歳、2歳ころまでは発達に特に不安を覚えるようなことは無く、発語も歩き出すのもごく一般的な年齢で出来ていました。
1,2歳児の保育園での保育参観時にはとにかくおとなしくて、大好きな先生にべったりな甘えん坊タイプの子として過ごしている様子も見てきました。
低年齢のうちは言語のコミュニケーションが難しいので大人が仲介するのが当たり前なので、その点は気付きようがありませんでした。
しかし3歳になり、保育園の進級の時期になって「まばたき」が気になるように。
「え、まばたき多くない?もしかしてチック?」
と、うっすらチック症のことは知っていたのですが、チックではなく目に異常があってのまばたきだったら大変だと思い、眼科を受診。
結果は「目の異常は見られないのでおそらくチックでしょう。そっと様子を見てあげてください」
とのことでした。その時初めて「この子は繊細なのかな」と思ったことを覚えています。
他にも、先生を介してお友達と遊ぶものの、「貸して」がなかなか言えない。
発語は普通にできる。けど「貸して」のタイミングで言えなくて、どうしてもおもちゃを取ってしまう。
そこで先生に「おうちでも貸しての練習をしてみてくださいね」と言われたときは正直ショックでした。帰りの車で運転しながら少し泣くくらいには。(笑)
「みんな出来てるのになんで、、」って
比べたところでどうしようもないのに勝手にほかの子と比べてしまっていました。
当時は「これって“育てにくい子”ってやつなのかな…発達障害??」と、正解がわからないままモヤモヤしていました。
園の先生や周りの反応で気づいたこと
その後もこまめに先生と情報を共有し、日々過ごして無事にまた進級の時期を迎えました。
そしてまたまばたきのチック。
前年のこともあり、うちの子は3月4月の卒入園や先生の異動など環境が変わりやすい時期にチックになりやすいかもと予想ができていたので、この時から焦ったりすることなく対応できていました。
が、チックにも変動が。
まばたきに加えて、鼻をすする、咳払いのチックも出てくるように。
とにかくそっと見守りつつ、穏やかに過ごせるように家ではのんびり過ごさせていました。
そして転機となった4歳児クラスでのお迎え時の出来事。
担任の先生から「○○くん、集団行動が苦手で、興味のない話だと歩きだしてしまう。
静かにしないといけないタイミングで注目を集めたくてか動いたり、声を出してしまう。
そして好きなことをしていると、自分の気の済むまで続けたくて気持ちの切り替えが難しい」
と。
先生や保育園に迷惑をかけてしまっていたんだと知って謝りました。
そして私も、長男がお葬式で少しの時間もじっとしていられなかったり(座って5分も持たないで駆け回る)、
何かで怒られても、怒られていることを理解できていない様子で、平気で何度も怒られることを繰り返したりしていたこともあり、
家で過ごす時間もどこかに行くときも常に長男に張り付いていないといけないような生活になってきた
ということをその先生に伝えると
「お母さん謝らないで。一緒に考えれば大丈夫だよ!
もしよければ市で運営している発達の教室があるから紹介するよ。」
と、発達教室なるものを紹介して頂きました。
もしかしたらここでショックを受けるのが普通の反応なのかもしれないのですが、
私は「もしかして発達障害?」と思っていても、旦那や同居の家族には理解を得られず
「子供ってこんなものだよ」と言われていたので今回の先生のお話や教室の紹介で正直私は
ようやく次に進める!!と安心したのも事実です。
発達相談から診断までの流れ
発達教室(月に1回でした)では、年齢ごとに分かれて体を動かしたり、細かい工作をして指先を使ったり、お返事や挨拶の練習などをする、を通して体や指先のぎこちなさや人とのコミュニケーションを先生方が見ている感じでした。
私たち親は、はじめましての人たちしかいなかったのですが、
「子供の発達に特性がある」という共通点があるので、あっという間に打ち解けて、今後の進学についてや療育のことなど相談することができました。
そしてその後は市の子育て課の方と面談をして、園での様子や家庭での様子を伝えました。
「もしお母さんが気になるようなら療育センターの受診もいいかもしれませんね」
とのとこで療育センター受診を決断。
やはり療育センターはいつでも混んでいて、この時4歳児で11月に療育センターに問い合わせ、
「就学前に診断して頂いて就学先も考えたい」と伝えたところ
「そうですね。就学前なのでなるべく早めに診察したいので2月に」
と考慮して頂き、問い合わせから3か月後に受診することができました。
正直もっと先になるかと思っていたので早めて頂いて感謝でした。
療育センターでは伝え漏れないようにしたくて、今までのことをノートにまとめてそれを提出し
先生もそれをもとに様々な聞き取りをしてくださいました。
そしてASDやADHDに関するチェックシートや問診票の記入をして
「特徴や特性を見る限りだとASDとADHDに当てはまることが多いですが、初診ですぐ確定とは行かないので、これから時間をかけて段階的に評価して行きます。」
ということで初回は終了でした。
そして数回受診の間に発達検査、知能検査などのテストなども行い、
「自閉スペクトラム症(ASD)とADHD(注意欠如・多動症)」との診断が出ました。
程度は軽いということでしたが、
特に言葉でのコミュニケーション能力が1歳半ほど実年齢より下でした。
そして「数の概念」が無い。とも言われました。
確かに1,2,3と順番に数えたりこれは何個!と答えたりすることは出来ても、
4の次は?と聞かれると分からない。5と6どっちが大きい数字?と聞いても分からない
など実際に数字苦手だなと思うことは多々ありました。
ですが「就学前なので、勉強が始まれば伸びる子もいるので焦らないでね」と主治医の
先生にも温かい言葉をいただきました。
診断を聞いた瞬間は、「やっぱりそうだったんだ」とホッとしました。
今、長男と向き合って思うこと

診断が出てからは、保育園の先生方が熱心に面談の時間を作ってくださり、就学に向けてや、日々の生活での接し方、ものの伝え方など様々なことを私と話し合って園全体で共有してくださいました。
そして、発達教室でお世話になった市の方とも密に連絡を取って、進学先の学校の見学を一緒に行ってくださったり、たくさん面談をして不安解消に向き合ってくださいました。
今現在、長男は6歳でピカピカの1年生です(*’ω’*)
支援級か通常級かでしばらく悩みましたが、本人の意思と、主治医、園や学校の先生、市の担当職員さんの勧めにより
まず1年生のうちはみんなスタートラインが一緒なので通常級
ということで通常級に通っています。
田舎のため保育園からみんな一緒で9人しかいないためサポートも手厚いという利点と
周りの方のご支援やご理解のもと楽しく学校に通えています。
今は3か月に1回程度の通院で、漢方(抑肝散)を服用していて、効果が出てきて少しづつですが
落ち着いて生活することができるようになってきています。
3歳のころに言っていた「くつしたの縫い目」は今はだいぶ気にならなくなって
今のところはなんでも履いてくれるまでになりました。
時にふと「このくつした嫌だ」の日もあるのですが(笑)
今後のことは後で考えるとして、今は今しかない長男の成長をしっかり見守って
多少のことではびくともしないメンタルで長男に向き合おうと思います。
同じように悩むママへ伝えたいこと
「うちの子だけ…?」って感じる日々、すごく不安ですよね。
でも実は同じ悩みを抱えている方って意外とたくさんいるんです。
誰かに相談するのは勇気がいるけど、保健師さん、保育士さん、児童発達支援センターなど、話せる場所はたくさんあります。
私もたくさん悩んでたくさん泣いた日々がありましたし、これからもきっと悩むことはたくさん
あると思います。
でも、「発達の特性」があるからダメ。とかそんなことは絶対ない。
それを個性としてどこか良い方向へ伸ばしていってあげるのが今私がやるべき事なのかな、と
考えて息子に向き合っています。
まずは「気になる行動」をひとつでもメモして、誰かに話してみてほしいなと思います。
まとめ
3歳で見え始めた発達障害のサイン。
あのときは毎日が手探りで、「私の育て方が悪いのかな…」と自分を責めてしまう日もありました。
でも今振り返ると、**「あのとき気づけてよかった」「相談してよかった」**と思える場面がたくさんあります。
そして、子どもの行動ひとつひとつに「理由」があると知ったとき、親としての見方も接し方も少しずつ変わっていきました。
「発達障害」と聞くと、どうしても不安が先に立ってしまうかもしれません。
でも、それは「ラベル」ではなく、**“子どもをより深く知るためのヒント”**だと今は感じています。
同じように「うちの子だけかも」と悩んでいるママがいたら、どうか一人で抱えこまないでください。
このブログが、「私も同じだったよ」と言えるきっかけになれたらうれしいです。
これからも、親子で一歩ずつ、ゆっくりでも前に進んでいきましょうね。
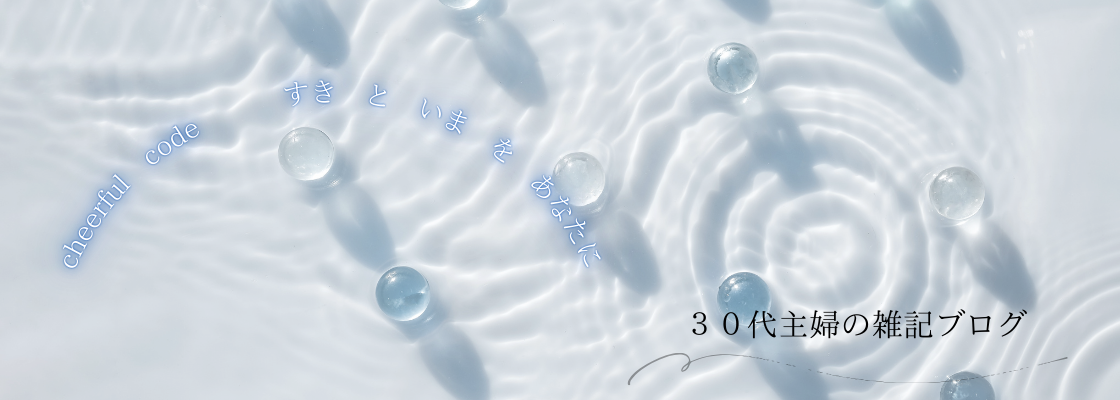




コメントを残す コメントをキャンセル